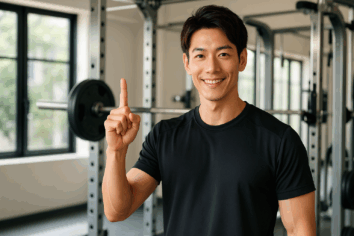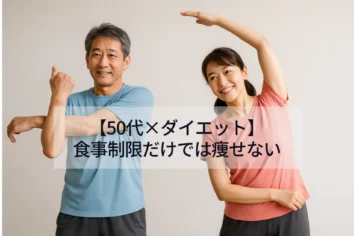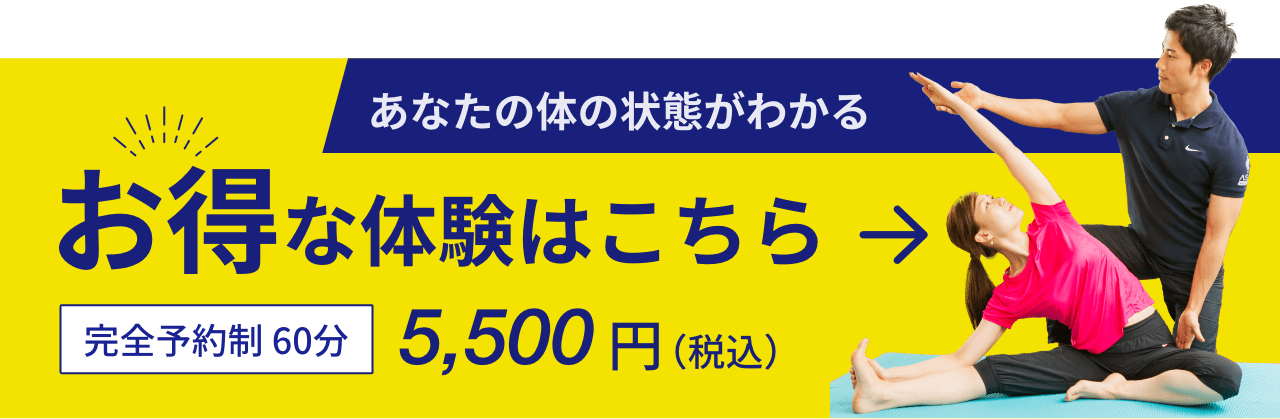2025.06.16Category: CONTENTSTags:小学生無料
運動会で差がつく!子どものスタートダッシュ練習法まとめ

運動会のかけっこで、スタートの瞬間に他の子に遅れをとってしまい、そのまま最後まで追いつけずに終わってしまう。そんな我が子の姿を見て「もう少し速くスタートできたらなあ…」と感じている保護者の方は多いはずです。
実は、スタートダッシュは技術と練習次第で大きく改善できる分野。生まれ持った足の速さに関係なく、正しい方法を覚えることで、お子さんがかけっこで自信を持てるようになります。
ちょっとしたコツを覚えるだけで驚くほど変わるもの。運動会本番に向けて家庭でもできるスタートダッシュの練習法を、分かりやすくお伝えしていきましょう。
目次
1.スタートダッシュの重要性
運動会のかけっこや短距離走では、最初の数秒間のスタートダッシュが競技全体の結果を左右する重要な要素となります。スタート時に一歩でも前に出ることができれば、そのアドバンテージを保ったまま有利にレースを進められるのです。
特に小学生の短距離走では、コースの距離が比較的短いため、スタートの良し悪しがタイムや順位に直結しやすくなります。たとえ普段から足が特別速いわけではないお子さんでも、スタートダッシュの技術を身につけることで、これまでより良い結果を残せるでしょう。
 吉野トレーナー |
スタートがうまくいくと精神的な余裕も生まれ、その後のレース運びにも良い影響を与えます。逆にスタートで出遅れると焦りが生じ、本来の力を発揮できないまま終わってしまうことも。 だからこそ、運動会に向けた準備として、スタートダッシュの練習に時間を割くことは非常に有効な手段です。 |
2.スタートダッシュが速くなる基本のポイント

☑姿勢とフォーム
スタートダッシュを成功させるためには、まず正しい姿勢を身につけることが不可欠。正しい方法を覚えれば、お子さんの走りは確実に変わります。
◎前傾姿勢の重要性
上半身を自然に前に倒し、重心が前脚にしっかりと乗るように意識しましょう。前の足のすねの骨の真下、内くるぶしの下あたりに重心を感じられるようになると、余計な力が抜けて効率よく踏み出せます。この前傾姿勢により、スタートの瞬間から前方向への推進力を最大限に活用できるからです。
◎手足の逆運動
右足が前にある場合は左手を前に、左足が前の時は右手を前に出してください。この逆の動きにより、1歩目を大きく力強く踏み出しやすくなるでしょう。最初は違和感があるかもしれませんが、慣れてくると自然にバランスが取れるように変わります。
◎目線の位置
走り出してから最初の10メートルの間は、自分の3歩先を見るようにします。この目線の位置により、自然な前傾姿勢を保ちながら加速していくことが可能。下を向きすぎると前傾が強くなりすぎて転倒の危険があり、上を向きすぎると前傾が足りずに加速できません。
☑タイミングの準備
◎リラックスの重要性
緊張で力んでしまうと、体の動きが硬くなり、素早い反応ができなくなってしまいます。スタート前には深呼吸をして、体と心をリラックスさせることが重要。肩の力を抜き、自然な呼吸を心がけましょう。
◎合図への即座反応
笛やピストルの音に対して即座に反応できるよう、普段から合図に合わせてダッシュする練習を積み重ねることが大切です。また、先生の合図の間隔やリズムを日頃から観察しておくと、本番でのタイミングを予測しやすくなるでしょう。
3.具体的な練習法
★壁押しトレーニング
まず、壁に向かって両手をつき、片足を後ろに引いてスタートダッシュの基本フォームを作ります。顔は前を向き、背中から足、腕が一直線になるよう意識しながら、その体勢を20〜30秒間キープしてください。
次に、壁を押しながら左右の足を素早く入れ替える動きを10回行います。この時、かかとは地面につかないよう上げたままにし、お腹の力(体幹)で壁をしっかりと押すことがポイント。
注意点 背中は反らさず真っすぐに保ち、体幹の力を意識して動作を行いましょう。この練習により、スタート時の正しい体重配分と筋肉の使い方を身につけることができます。
★反射神経トレーニング
スタートダッシュでは、合図に対する反応速度が勝負を分ける重要な要素となります。反応の速さは練習で確実に伸ばせるものです。
保護者の方や練習パートナーに「よーい…ドン!」とランダムなタイミングで合図を出してもらい、その瞬間に全力でスタートする練習を行いましょう。合図の間隔を意図的に変化させることで、より実戦に近い状況での反応能力を鍛えることができます。
さらに効果的な練習として、時には合図以外の音(フェイント)も混ぜて、正しい合図だけで動けるように反射神経を鍛えてください。これにより、本番での集中力と判断力も同時に向上させることが可能になります。
★フォーム確認ラン
スタートの姿勢を作り、少し前につんのめるくらいの前重心を意識してからダッシュを開始します。転ばない範囲で思い切り前に体重をかけることで、効果的な前傾姿勢でのスタートを体感できるでしょう。
この練習では距離よりも、正しいフォームでスタートできているかどうかに重点を置いて行います。最初はゆっくりでも構いませんので、確実に正しい動作を身につけることを優先してください。
★10秒アクション体操
体の軸を感じさせ、インナーマッスルを目覚めさせる簡単な体操を1日10秒ずつ行いましょう。姿勢や重心を意識しながら体操することで、体の余計な力が取れやすくなり、より効率的に動けるようになります。
まっすぐ立った状態で軽く前傾し、その姿勢を保ちながら足踏みをしたり、腕を前後に振る動作を行ってください。短時間でも毎日継続することで、体の動きが自然と改善されていくはずです。
詳しくはこちらの動画を御覧ください🎦
4.保護者のサポートポイント

お子さんのスタートダッシュ向上には、保護者の方の協力とサポートが欠かせません。家族の応援が一番の力になるものです。
◆練習環境の整備
家の庭や近所の公園など、安全に走れる場所を確保し、保護者の方がスターター役となって一緒に練習してあげましょう。お子さんにとって、信頼できる大人と一緒に練習することは、技術向上だけでなく精神的な安心感にもつながるのです。
◆段階的な練習進行
最初はケガ防止のため、ゆっくり・短距離での練習から始め、お子さんが慣れてきたら少しずつスピードと距離を伸ばしていきましょう。無理をせず、お子さんのペースに合わせて進めることが継続的な上達のポイントです。
◆励ましと評価
練習中は小さな改善点でも見逃さずに褒めてあげることで、お子さんのモチベーション維持につながります。たとえば「今のスタート、前より速かったね」や「姿勢が良くなったね」など、具体的な評価を伝えることが効果的です。
5.よくある失敗と克服法
スタートダッシュの練習でよく見られる失敗例と、その対策方法をご紹介します。多くのお子さんに共通するパターンをまとめました。
△力みすぎて体が硬くなり出遅れる
緊張や気合が入りすぎて、体全体に余計な力が入ってしまうケース。この場合は、深呼吸で体をリラックスさせ、反射神経トレーニングを通じて自然な反応ができるように練習しましょう。「力を入れる」のではなく「素早く反応する」ことに意識を向けることが重要です。
△手と足が同じ方になって踏み出せない
手と足を逆に動かせずに、同じ側の手足が前に出てしまう失敗のケース。構えた時に意識的に手足を逆にする習慣をつけ、ゆっくりとした動作から始めて体に覚え込ませることで改善できます。
△スタート時に目線が上がり加速できない
緊張やゴールを意識しすぎて目線が上がってしまい、前傾姿勢が取れなくなるケースです。目線は自分の3歩先を意識し、徐々に前を見るようにする練習を重ねることで、自然な加速ができるようになるでしょう。
△後ろ足で蹴りすぎて滑ってしまう
地面を強く蹴ろうとしすぎて、足が滑ったり体が後ろに残ってしまう失敗。この場合は、前足への重心移動と前に抜ける感覚を重視し、「蹴る」よりも「前に進む」ことを意識した練習を行いましょう。
まとめ
スタートダッシュは、生まれ持った運動能力に関わらず、正しい技術と練習によって誰でも向上させることができます。今回ご紹介した練習法は、特別な設備や道具を必要とせず、家庭でも気軽に取り組めるものばかりなので、運動会本番に向けて、お子さんが自信を持ってスタートラインに立てるよう、保護者の方の温かいサポートのもとで練習を積み重ねてください。
正しいフォームの習得、反応速度の向上、そして精神的な準備が整えば、きっと今までよりも良い結果を出すことができるはず。
 井上コーチ |
大切なのは、結果だけでなく、お子さんが努力を重ねるプロセスを大切にすること。練習を通じて得られる達成感や自信は、スポーツだけでなく、お子さんの様々な分野での成長にも良い影響を与えることでしょう。 |
運動会当日、お子さんが堂々とした姿でスタートダッシュを決める姿を、ぜひ期待して見守ってあげてください。
小学生からでも体験を受け付けております! ぜひご予約ください。
- あわせて読みたい