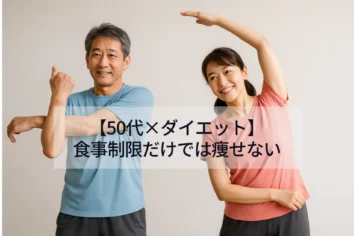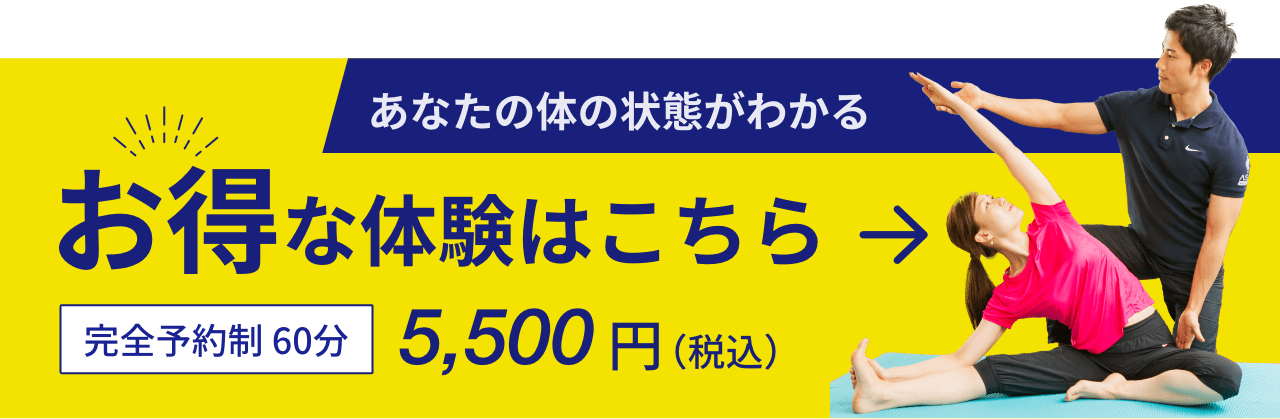2025.06.04Category: CONTENTSTags:小学生無料
運動会でビリを卒業!子どもが速くなる“走り方のコツ”とは?
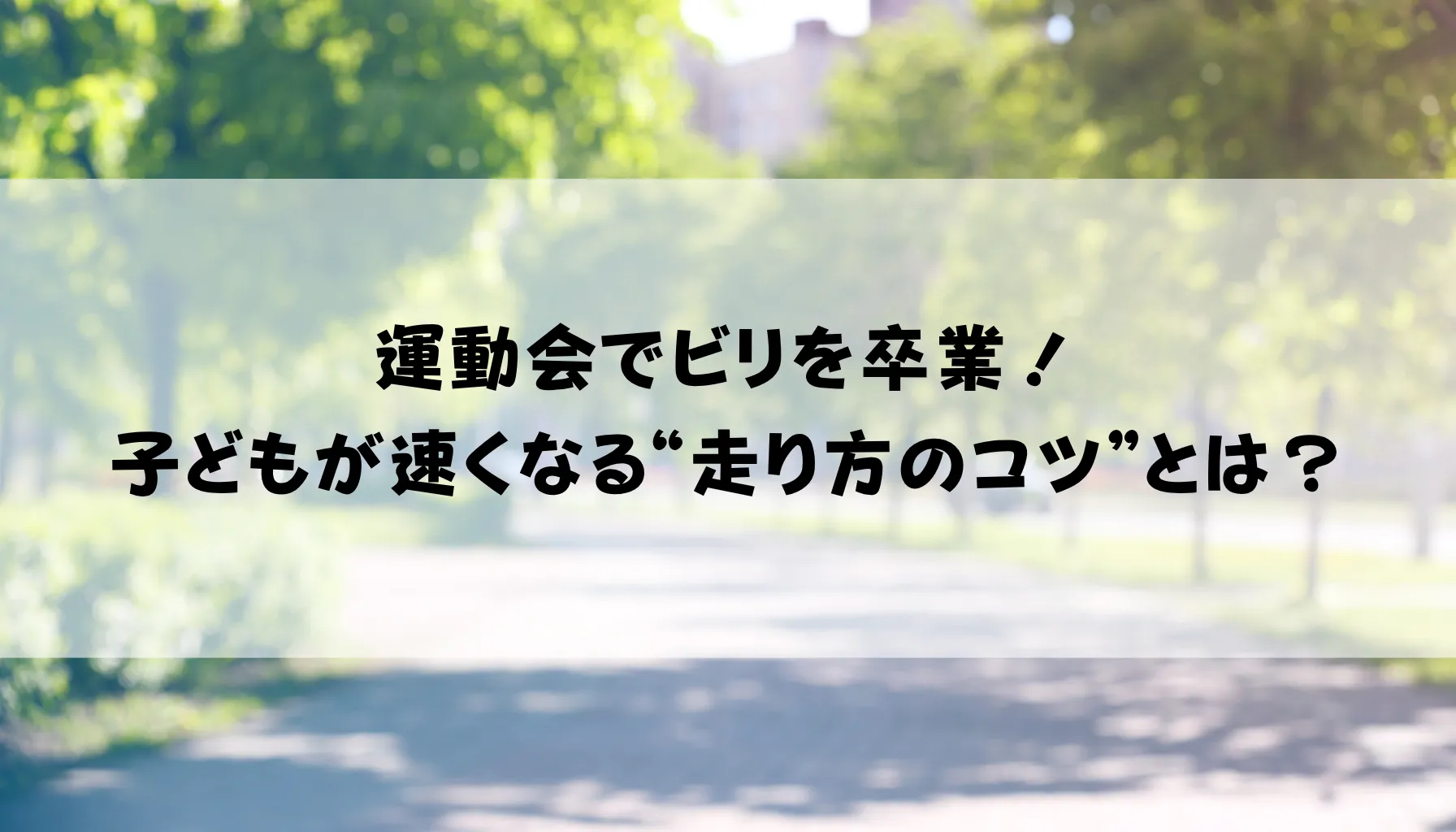
「うちの子、足が遅くて運動会が心配…」「ビリになったら可哀想」
——そんな不安を抱えている保護者の方も多いのではないでしょうか。特に小学生になると、かけっこの結果が子どもの自信にも大きく影響します。
この記事では、運動会のかけっこで速く走れるようになるための具体的な練習方法や、走り方のコツをわかりやすく解説します。また、フォームの改善や、家庭でも取り入れられる簡単なトレーニングも紹介します。
かけっこが苦手な子でも変わるチャンスはあります。親子で一緒に取り組めば、楽しみながら力を伸ばすことができます。読み終えるころには、「やってみよう」と前向きな気持ちになれるはずです。運動会で笑顔のゴールを目指しましょう。
目次
運動会のかけっこで速く走るには?親ができるサポートとは
運動会で速く走るためには、子ども自身の頑張りだけでなく、家庭での声かけや練習環境も大切です。小学生のかけっこは、体の使い方や気持ちの持ち方で大きく変わるものです。特に足が遅いと感じたとき、ただ走らせるだけではなかなか上達しません。まずは、足が遅く見える原因を正しく知り、子どものやる気を引き出す関わり方を意識しましょう。
まずは現状把握!「足が遅い」と感じる原因を見極めよう
お子さんが「かけっこが苦手」と感じている場合、原因をしっかり知ることが上達への第一歩です。苦手だと感じる理由を大きく2つに分けると、「身体の使い方」と「メンタル面」があります。
①身体の使い方
小学生の走り方には、まだまだ個人差が大きくあります。フォームが安定していなかったり、腕の振り方が合っていなかったりすることも珍しくありません。特に足だけで速く走ろうとすると、バランスを崩してしまい、かえってスピードが落ちてしまうことがあります。
また、姿勢が前かがみになりすぎたり、逆に体が反りすぎていたりすると、推進力がうまく働きません。足の動きよりも、体全体を使ってリズムよく走れているかどうかが大切です。
②メンタル面
そして、足が遅いと決めつける前に、走ることに対する自信や気持ちの持ち方も確認してみてください。緊張しやすい性格だったり、過去に失敗して苦手意識を持っていたりするケースもあるからです。
原因を一緒に探してみることで、子どもは「ちゃんと見てもらえている」と安心します。その気持ちが、次の一歩につながるきっかけになります。
親の声かけがカギ!子どものやる気を引き出す方法
かけっこの練習で意外と重要なのが、親の声かけです。子どもは大人が思っている以上に、親の言葉に敏感です。たとえば、
〇「もっと速く走ってよ」
〇「なんで遅いの?」
といったネガティブな声かけは、やる気をそぐだけでなく、自信を失わせてしまう原因になります。逆に、
〇「今のフォーム良かったね」
〇「前よりスムーズだったよ」
といった前向きな声かけは、子どもにとって大きな励みになります。小さな成長をしっかり見つけて、言葉にして伝えてあげてください。
さらに、練習を一緒にやる姿勢を見せることも効果的です。
例えば、親が伴走したり、「今日は一緒に勝負してみようか」とゲーム感覚で取り組むことで、子どもは自然と楽しみながら集中できます。
かけっこをする上で目指すのは「勝たせる」ことだけではありません。「がんばって走るのが楽しい」と思える経験を積むこと。それが、結果的に子どもを速くする一番の近道になります。
小学生でも変わる!かけっこの基本フォームと改善ポイント

かけっこで速く走るためには、正しいフォームを身につけることが大切です。小学生のうちは体の使い方がまだ未熟で、ちょっとした癖がスピードに大きく影響します。
この章では、足が遅く見える原因となる「悪いフォーム」の特徴を紹介し、どのように改善すれば速く走れるかをわかりやすく解説します。親子で一緒に意識しながらトレーニングすることで、走り方は確実に変わっていきます。
足が遅い子に多い「悪いフォーム」の特徴とは?
走るときのフォームは、見た目以上に大切な要素です。特に足が遅いと感じる子どもには、いくつかの共通した特徴が見られます。たとえば、姿勢が前のめりになりすぎていたり、逆に上半身が反ってしまっていたりすることがあります。このようなフォームでは、体の重心がうまく使えず、スピードが出にくくなってしまいます。
また、腕の振りが小さかったり、足を引きずるような走り方をしている子も多く見られます。これでは推進力が足りず、思うように前に進むことができません。目線が下がっているのもよくあるパターンで、これもスピード低下につながる原因のひとつです。
このような「悪い癖」は、本人が気づきにくいものです。まずは動画を撮って一緒に見てみると、子ども自身もフォームに意識を向けるきっかけになります。どこを直せばいいのかが分かれば、改善のステップも見えてきます。
速くなるための正しいフォームと姿勢のコツ
かけっこでスピードを上げるためには、正しいフォームを身につけることが重要です。特に小学生のうちは、成長に応じて体のバランスが変わりやすいため、自然と崩れたフォームになってしまうこともあります。これを直すために、次の3つのポイントをしっかり押さえるだけで、大きな改善が見込めます。
①「姿勢」
まず意識してほしいのが「姿勢」です。走るときは、背筋を伸ばして少し前傾姿勢をとるようにしましょう。上半身を反らせると後ろに重心がかかりスピードが落ちます。逆に、前のめりすぎるとバランスを崩しやすくなるため、やや前に倒す感覚を意識するとちょうど良い姿勢になります。
②「腕の振り」
次に大事なのが「腕の振り」です。肘を軽く曲げて、肩からしっかり後ろに引くように動かすと体が前に進みやすくなります。腕を横に大きく振る子が多いですが、これではエネルギーが逃げてしまいます。コンパクトに、でも力強く後ろに引くのがポイントです。
③「足の動き」
「足の動き」も重要です。膝をしっかり上げて、地面を押すように走ることで、効率的に加速できます。足を高く上げようとしすぎる必要はありませんが、足を引きずるようにしているとスピードは出ません。地面を「押す」感覚でリズムよく走るようにしましょう。
これらのポイントは、すぐに完璧にできるようになるものではありませんが、少しずつ意識していくことで確実に変化が現れます。まずは一つだけでも集中して取り組むと、子ども自身も手ごたえを感じやすくなります。焦らず、一歩ずつ改善を目指しましょう。
フォーム改善のための親子トレーニング方法
走り方の改善は、意識するだけでなく、実際に体を動かしてみることで定着します。小学生にとっては、ただ「こうしなさい」と教えるよりも、一緒に楽しくやることで自然と身につきやすくなります。ここでは親子で気軽に取り組める、かけっこのフォーム改善に効果的なトレーニングを3つ紹介します。
①「もも上げ練習」
まずおすすめしたいのは「もも上げ練習」です。片足ずつしっかりと膝を高く上げて、リズムよくその場で足踏みをする運動です。腕を大きく振りながら行うことで、腕の使い方も一緒に確認できます。テンポを変えたり、回数を数えながら行うと、子どもも飽きずに取り組めます。
②「スキップ」
次に効果的なのが「スキップ」です。一見遊びのようですが、スキップはリズムよく走る感覚をつかむのにぴったりです。足のバネを使いながら体を前に進めるため、自然とフォームが整っていきます。親も一緒にやってみると、子どもはさらに楽しんでくれるでしょう。
③「腕振りだけの練習」
もう一つ試してほしいのが「腕振りだけの練習」です。鏡の前や壁の前に立ち、肘を曲げて腕を後ろにしっかり引く動作を確認します。壁に手が当たらないように意識することで、腕が体の真横を通る正しい振り方が身につきます。数回でも繰り返すことで、走るときに自然と良い形が出てきます。
こうしたトレーニングは、1日数分でも継続することが大切です。無理に長時間やらせるよりも、少しずつ毎日続けることの方が効果的です。そして何より、親が「一緒にやろう」と声をかけることで、子どものモチベーションが上がります。楽しい時間を共有しながら、少しずつフォームを改善していきましょう。
運動会に向けたかけっこ練習メニュー【自宅・公園でOK】

かけっこの練習は、特別な道具や広い場所がなくても取り組めます。自宅の庭や近所の公園など、身近な場所でできるメニューを取り入れることで、子どもは無理なく走る力を伸ばせます。ここでは、毎日短い時間でも続けられる練習方法や、子どもが楽しめる工夫、そして継続するためのコツを紹介します。親子で取り組むことで、運動会へのモチベーションも自然に高まります。
1日10分でOK!短時間で効果が出る練習法
小学生の集中力は長く続きにくいものです。だからこそ、1日10分程度の短い練習が効果的です。例えば、自宅の前や公園で「30mのダッシュ」を数本行うだけでも違いが出てきます。スタートからゴールまで全力で走る経験を繰り返すことで、スピードを出す感覚が身につきます。
ダッシュの合間には、休憩をはさみながらフォームを意識した「もも上げ」や「腕振り」なども取り入れましょう。短時間でも、正しい体の使い方を繰り返すことが大切です。10分程度なら子どもも嫌がらず、習慣にしやすい練習量です。
楽しみながら走力アップ!ゲーム感覚でできるトレーニング
練習を続けるうえで一番の課題は「飽き」です。子どもが退屈に感じないよう、遊びながら取り組めるメニューを入れると良いでしょう。たとえば
〇「親子競争」
〇「おにごっこ」
〇「スタートだけ全力で競うゲーム」
といった遊びも立派なトレーニングです。走ること自体が遊びになれば、自然とスピードも上がっていきます。
子どもが「もっとやりたい!」と思えるような練習を取り入れることで、かけっこに対して前向きな気持ちが芽生えるでしょう。また、親も一緒に楽しむ姿を見せることで、練習が家族の時間にもなります。
練習頻度と継続のコツ|飽きさせない工夫とは?
効果を出すには「毎日コツコツ」が理想ですが、無理をして続かなくなるよりも、週に数回でも続ける方が長い目で見て良い結果につながります。たとえば平日は5分程度、休日は少し長めに公園で練習するといったバランスが最適です。
継続の秘訣は「変化をつけること」です。同じメニューばかりだと子どもはすぐに飽きます。ダッシュ、スキップ、もも上げなど、日によって組み合わせを変えましょう。練習の後に「今日はここが良かったね」と一言伝えるだけでも、子どものやる気が続きます。
短い時間でも楽しく続ければ、子どもの走り方は確実に変わります。親子での習慣にして、運動会までの時間を前向きに積み重ねていきましょう。
 井上コーチ |
「かけっこの練習」ではなく、「遊んでいて、気が付いたら走るのが速くなっていた」という状況が理想的です! |
子どもが速くなるための走り方のコツ【すぐに試せるテクニック】

運動会のかけっこで少しでも速く走れるようになるためには、特別なトレーニングだけでなく「走り方のちょっとしたコツ」を身につけることが大切です。ここで紹介するのは、今からでもすぐ試せるテクニックばかり。小学生でも覚えやすく、当日の走りにも直結します。子どもがレースのときに自信を持って走れるように、日々の練習に取り入れてみてください。
スタートダッシュで差をつける!構えと出だしのポイント
かけっこは「スタートで決まる」と言われるほど、最初の一歩が重要です。まずはスタートラインでの構え方を見直しましょう。腰を少し落として前傾姿勢になり、片方の足を少し後ろに引きます。体重を前足にかけることで、合図と同時にスムーズに飛び出せます。
出だしの際は、思い切って前に倒れ込む感覚で踏み出します。最初の3〜5歩は腕を強く振り、地面を力強く蹴ることを意識しましょう。この短い区間でリードできれば、その後の走りも楽になります。
腕の振りと足のリズムを意識して加速
スタート後は、加速を維持するために腕と足の連動が大切です。腕を大きく振ると足も自然と速く動くため、体全体が前に進みやすくなります。肩から後ろにしっかり引く意識を持ち、リズム良く動かしましょう。
また、足はリズム感を大切にします。膝を軽く上げ、地面を押すようにして走ると力が伝わります。最初はテンポがバラバラでも、親が「1、2、1、2」と声をかけながら走ると自然とそろってきます。腕と足が同じリズムを刻めるようになると、かけっこのスピードが一段と上がります。
ゴール前で抜かれないための走り切りテクニック
最後の直線で抜かれて悔しい思いをした子も多いのではないでしょうか。ゴール前こそ気持ちを切らさず走り切る工夫が必要です。ゴールテープを「胸で突き抜ける」イメージを持つと、最後までスピードが落ちません。
また、ゴールの少し先を見て走ることもポイントです。目線が下がるとスピードが落ちやすくなるので、少し先を見て体を前に押し出すように走ると最後の一歩まで全力を出せます。
こうした簡単な工夫を取り入れるだけで、かけっこの走り方は見違えるように変わります。本番で子どもが自信を持って走れるよう、日常の練習で繰り返し意識させましょう。
 井上コーチ |
スタート、走っている途中、ゴール前……全部気を抜けないですね! |
かけっこに自信がない子でも大丈夫!メンタル面のサポート術

かけっこの結果は、技術だけでなく気持ちの強さにも左右されます。特に過去に転んだりビリになった経験がある子どもは、本番を迎えるだけで緊張してしまうことがあります。そんなときこそ、親がどのように気持ちを支えるかが大切です。ここでは、子どもが自信を取り戻し、楽しく運動会に臨めるようになるためのサポート方法を紹介します。
失敗が怖い子どもへの声かけの工夫
「転んだらどうしよう」「また遅かったら恥ずかしい」
こういった不安を抱えている子どもには、安心させる言葉が必要です。
「失敗しても大丈夫だよ」「最後まで頑張るのがかっこいいよ」
このように前向きな言葉で伝えることで、子どもは気持ちを落ち着けやすくなります。
また、結果だけを褒めるのではなく、練習に取り組む姿勢をしっかり認めることが重要です。
「昨日より姿勢が良くなったね」「ちゃんと腕が振れていたね」
のように、具体的にできていたところを言葉にすることで、自信が少しずつ積み重なります。
勝ち負けだけじゃない!成功体験をつくる工夫
かけっこに苦手意識を持つ子どもには、「できた」という小さな成功体験が必要です。たとえば、タイムを少し縮められた、スタートがうまくできた、フォームが整ってきたなど、小さな進歩を見つけて褒めると効果的です。
さらに、親子で競争するときは、あえて親が少し手を抜いて子どもに勝たせることも一つの方法です。「勝てた」という実感は、やる気を大きく引き出します。このような小さな成功の積み重ねが、運動会で走る自信につながります。
他の子と比べない「自己ベスト」重視の考え方
多くの子どもは、無意識に友達と自分を比べています。そして、負けるたびに落ち込んでしまうのです。そんなとき、親が「誰かより速いかどうか」ではなく「昨日の自分より良くなったかどうか」に焦点を当てる声かけをすると、気持ちが変わります。
「前よりスタートがうまくいったね」「ゴールまでしっかり走れたね」
こういった他人と比較せず、自分自身を認めてくれる言葉は、子どもの自己肯定感を育てます。結果よりも成長を認めることで、かけっこへの前向きな姿勢が自然と育ちます。
まとめ|運動会のかけっこ練習は、子どもの未来を変えるチャンス

この記事では、運動会のかけっこで子どもが速く走れるようになるための考え方や、フォーム改善、日々の練習法、そしてメンタル面のサポートまでを紹介しました。どれも特別な道具をそろえなくても、自宅や公園で親子一緒に取り組める方法です。
大切なのは、短時間でもいいから練習を続けることと、小さな成長を見つけて褒めること。この積み重ねが、子どもの自信を育み、本番でも笑顔でゴールを駆け抜ける力になります。
これから始めるなら、まず子どもの走る姿をしっかり観察して、良い点と改善できそうな点を一緒に話してみましょう。 そして今日から5分でもいいので、親子で練習を始めてください。親が寄り添ってくれるだけで、子どもは前向きな気持ちでスタートラインに立てるようになります。
- あわせて読みたい