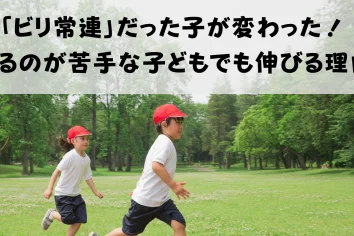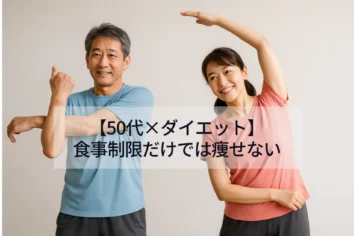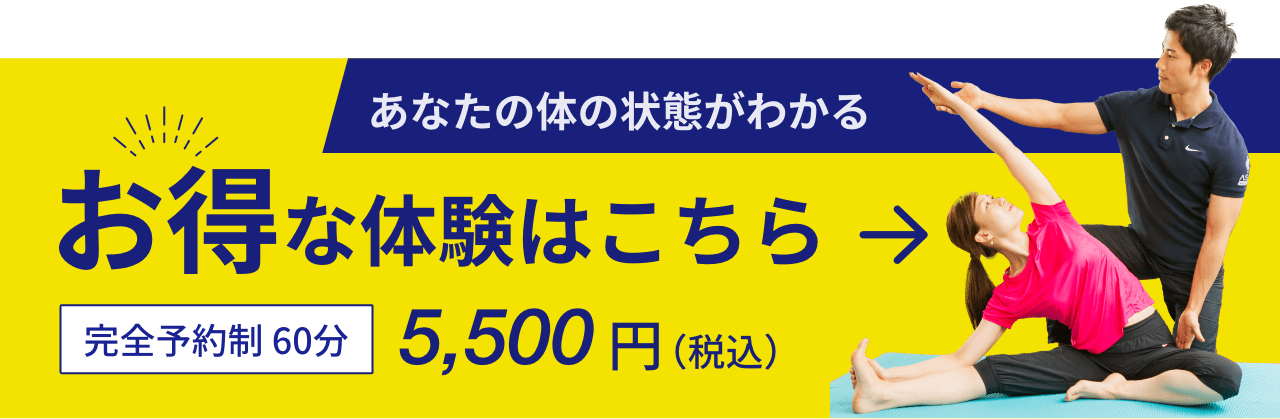2025.07.25Category: CONTENTSTags:健康小学生無料
生まれつきでは決まらない!「走るのが得意な子」がしている日常習慣とは?

「うちの子、走るのが苦手かも…」そんな悩みをもつ保護者の方へ。
子どもが、走るのが得意になるために必要なのは「生まれもった才能」よりも「日常の習慣」です。走力アップは、かけっこの練習だけでなく、外遊びや生活の中のちょっとした工夫でも伸ばすことができるのです。
この記事では、走るのが得意な子の日常習慣や、家庭ですぐに取り入れられる運動についてご紹介します。
読み終えたあとには、「まずこれから始めてみよう」と前向きな気持ちになれる内容です。親子で楽しみながら、走る力を伸ばしていきましょう!
目次
走るのが得意な子どもは何が違う?習慣で変わる「走る力」

子どもの「走る力」は、生まれつきの才能で決まるものではありません。
生活の中の環境や、習慣次第で後天的に伸ばせる能力の一つです。
 |
運動神経がいい=遺伝や生まれつき、と思われがちですが、実は違うんです。多くの場合、子どもの頃の運動経験や日常習慣が、体の動かし方や反応の速さといった力に大きく影響します。つまり、日頃の運動習慣次第で、走る力を伸ばすことができるのです。 |
生まれつき走るのが得意なわけじゃない?運動神経は習慣で伸ばせる
「うちの子は運動神経がないから…」と悩む保護者の声をよく聞きます。
いわゆる「運動神経」とは「体の動かし方がうまい」「反応が速い」といったイメージで使われており、これらは「後天的に伸ばすことができる能力の集まり」とされています。
特に幼児期から小学生の間は、成長にともなって体の動かし方を覚える時期。だからこそ、早いうちから「楽しく体を動かす経験」を積み重ねていくことで、運動能力や走力アップを目指すことができるのです。
「走るのが得意な子」は、生まれ持った能力ではなく、日常の中で体をよく動かす「経験」を積んできた子とも言えるのです。
運動習慣がある子は、運動能力が高い傾向にある
スポーツ庁が2024年度に実施した令和6年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」では、 運動習慣と結果の関係性を分析しています。
週に60分以上運動する習慣のある小学生や中学生は、走る・跳ぶ・体のバランス・持久力など、すべての項目で高い体力テストのスコアを記録していることが明らかになりました。

令和6年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果:スポーツ庁
この結果は、「走る力=才能」ではなく、普段から体を動かす習慣が、その土台を作っているという証拠です。
「走るのが得意な子ども」に共通する日常の習慣とは?

走るのが得意な子どもには、共通して見られる習慣や環境があります。
「特別な練習をしているわけでもなさそうなのに、なぜか速い」そんな子の秘密は、日々の何気ない行動に隠れていることが多いのです。
ここでは、走力アップにつながる日常の過ごし方を解説します。
走るのが得意な子どもは、日常生活でよく体を動かす習慣がある
走るのが得意な子は、特別なトレーニングをしているわけではなく、日常の中でよく体を動かしています。たとえば、通園・通学時に歩いたり走ったりする、外遊びの時間が毎日あるなど、意識せずとも体を動かす機会が確保されている家庭が多いのです。
また、休日は親子で公園に行く、買い物は徒歩で移動するなど、生活の中で「体を使うルート」が組み込まれていることもポイントです。
こうした習慣の積み重ねが、走るために必要な基礎体力や動作の土台になります。
日常の遊びの中で、走る力の土台を伸ばしている
走るのが得意な子どもたちは、日常の遊びの中でいろいろな動きを経験しています。
「速く走る」ためには、バランスをとる力や瞬時に動きを切り替える力、体をコントロールする力など、複合的な動きも重要です。
外遊びでは、それらの動きを多く経験することができます。
たとえば、鬼ごっこには「急に止まる・方向を変える・交わす」、ケンケンパのような遊びでは「バランスをとる」、公園の遊具では高いところから飛び降りるときにしっかりと「踏ん張る」などの要素があります。
楽しく遊ぶ中で自然と多様な動きを経験し、こうした動作が自然と身についていくことで、走る力の伸びにもつながっていくのです。
また、遊びを通して体を動かしているとき、子どもは「運動している」という意識ではなく、ただ「楽しいから夢中になって動いている」状態です。このような楽しさの中で経験を重ねていくことが、無理なく走る力を育てるうえでとても効果的です。
走るのが得意な子どもを育てる親の関わり方

どんなに効果的な習慣でも、子ども自身が「続けたい」「がんばりたい」と思えなければ長続きしません。だからこそ、家庭での関わり方がとても大切です。
子どもの気持ちを尊重しながら、「走るのが得意な子ども」へと育っていくサポートをしていきましょう。
ここでは、無理なく前向きに続けられる工夫や、親としてできる声かけのポイントをご紹介します。
走る力を伸ばす習慣づけには「やらされ感ゼロ」が重要
子どもにとって、走ることや運動そのものが「楽しい活動」として根づくかどうかは、最初の印象や日々の声かけが大きく影響します。
たとえば、「さあ、走る練習するよ!」と一方的に決めてしまうと、義務的なものに感じてしまうこともあるでしょう。特に「走るのが苦手」と子ども自身が感じている場合、運動に積極的に向かえない場合もあります。
そこで大事なのは、子どもが「自分で選んだ」と思えるような工夫です。
「公園で走ってみる?」「自転車とどっちが速いか競争してみる?」など、楽しみながら主体的に関われる選択肢を提示してあげましょう。
変化を言葉にして伝えることが習慣化と自信アップに効果的
 |
「この前よりいいフォームだったね」など、日々のちょっとした声かけでも、子どもは「またやってみようかな」という気持ちになります。結果ではなく、過程や小さな成長に目を向けて伝えてあげることで、運動が「やらされるもの」から「楽しいもの」に変わっていきます。 |
運動能力は、多くの場合、短期間で劇的に変化が訪れるものではありません。子どもは、自分が成長していることに気づかないまま、「もうやりたくない」と思うことも。
そのため、親がその変化に気づいて具体的に言葉にして伝えることが、習慣の定着にとって重要です。
「昨日より長く走れたね!」「前よりも腕の振りがかっこよくなってるよ」など、小さな変化で構いません。
大事なのは、「結果」よりも「変化」や「努力」を認めることです。
このような関わりを積み重ねることで、子ども自身も「がんばったら変われる」と感じやすくなり、自信につながっていきます。
やがてそれが、「走ることが好き」という思いに変わっていくのです。
まとめ|「走るのが得意」は、今日から少しずつ育てられる
走るのが得意な子どもに共通するのは、特別な才能ではなく、日々の中で積み重ねられた「習慣」です。
遊びの中で体を動かすこと、走る楽しさを実感すること、そして続けたいと思えるような家族の関わり方。
こうした毎日の工夫やサポートが、子ども自身の「できるかも」「やってみたい」という気持ちを育てていきます。
「少し遠回りして公園を歩く」「遊びながら体を動かす時間を作る」「前より速くなったねと声をかける」など、小さな一歩でも、走る力を育むきっかけになります。
走るのが得意な子どもを育てる習慣は、家庭の中からつくっていけます。
「どう関わればいいかわからない」「運動が苦手な子でも大丈夫かな」とお困りごとがあれば、専門のサポートを受けてみるのも一つの方法です。
小学生も体験受付中なので、ぜひお気軽にお申し込みください。
- あわせて読みたい